はじめに
中村咲太さんの記事はこちらから。

前回の記事はこちら。
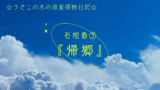
『鞍馬山と祇園祭』
話は中村咲太さんのリトリート後に遡る。
八重山の旅をしたのが9月中旬から10月初旬、その年の7月半ばにわたしは京都にいた。主な目的は、日本古来から受継がれてきた體術の入門講座を受けるためである。そこに抱合せて、理屈なしに大好きな鞍馬山と、琵琶湖に浮かぶ竹生島へ行く予定を一緒に組んでいた。今回はさらに、地元に戻りがてら関東の友達にも会って帰郷する予定である。まさに列島縦断の旅だ。
今回はお金の節約と滞在時間の確保のために、京都までの往路は夜行バスを使うことにする。早朝6時とか7時に京都駅に到着し、そこからまず鞍馬寺を目指す。
鞍馬寺は京都市の北に位置し、京都駅から出町柳駅まで出て、出町柳駅から叡山電鉄に乗り換えて山を登っていく。約一時間の道のりである。この叡山電鉄、車両によっては窓が大きくくり抜かれ、夏は山の緑を、そして秋は錦に色づく紅葉の中を走るので、特に秋は夜まで紅葉を目当ての観光客で賑わう。
わたしは親戚が京都滋賀に住んでいる関係で、子どもの頃から鞍馬寺には何度か来たことがある。物心がつくにつれて、何となく霊性の高さを感じさせるこの山とお寺に心惹かれるようになった。まず、お寺にも関わらずお祀りしているご本尊が「尊天」と呼ぶ宇宙の真理であること。そして金星との縁がとても深い場所であるためだ。お寺なのに、何て先進的なのだろう。
わたしは子どもの頃から太陽系の惑星や、その中でも特に金星が好きだった。セーラームーンを特に熱心に見ていた訳ではないが、一番好きなのは金星を守護星に持つセーラービーナスだった。そして、退職後にスピリチュアル動画を見漁って発見したオムネク・オネクという女性も、金星から来て地球人の女の子に入れ替わった人だった。その女性が語る金星の様子に異様に惹かれたものである。そしてこのオムネク・オネクさんが、実はわたしが中学生の時に熱心に読んでいた作者の本『シーラという子』に登場する実在する主人公シーラだったことにも驚愕させられた。これもまた、金星が繋ぐ深い縁のように感じる。
確か、鞍馬寺まで登る山道の途中に置かれている像にも、サナトクマラが金星から降り立った地として説明がなされていたと思う。サナトクマラが金星出身なのかどうかは分からないが、この日本の京都の山の中に、金星とサナトクマラですって。全く繋がらなくて不思議な感じがするが、そこを祀り守る地として鞍馬寺が設けられたのだとすれば実に興味深い。2017年に初めて一人で参拝した折には、本殿の恐らく千手観音菩薩がいらっしゃる御簾の奥から「よく来た」と、わたしの頭に向かって言葉が飛んできた。当時から恋焦がれていたと言ってもいい場所だった故に、一人本殿で涙ぐんだ思い出が印象深い。本殿までの山道は常人の体力であればなかなかきつい。子どもの頃は本殿までロープウェイで登ったが、今日は再度地上から歩いて参ろうと思う。
わたしは元々体力的にはそんなに強くなく、持久走は中の下から下の上と言ったところである。更に元々不眠症氣味であることに加えて、眠れない夜行バスでの長距離移動からの鞍馬山山道はわたしの体には苦しく、本殿に着く頃には汗をかいて息も切れていた。境内にある椅子に腰掛けるとしばらく動く氣力が出なかった。スピリチュアルの情報を漁っている中で、霊性が開いてくると柱一本一本とも話ができるようになるという話を聞いたことがあるが、わたしはそんな体験をしたことはない。なんだけれども、この日は疲れで朦朧としている間に本殿の両脇に狛犬として置かれている虎(だと思う)と、その手前にある大きな二つの灯籠と心の中でお喋りをしてみる氣になった。自分とは全く違う声が聞こえると言うよりは、子どもが独り言でおままごとをする感じである。獅子は男の子、灯籠は女性で、灯籠は結構氣位が高い性格をしていた。もし、狛犬や灯籠とお喋りをしたことのある方がいたら、どんなやりとりをしたのか教えてほしい。しばらくそんなことをして時間を潰しながら、体を休めた。
本殿では、前回のように奥から言葉が飛んでくるようなことはなかった。その代わり、中村咲太さんの講座で学んだワンネス・チャネリングというものを試してみたところ、言葉や映像ではなく、立ったまま体が円を描くように揺れ始めた。わたしの近しい方に、神社や聖地に行くと勝手に体が動き出すという人がいるが、そんな感じだった。とは言え、何を受取ったのかはよく分からない。本殿の地下には更に灯りを落とした拝殿があり、奥に三体の像が置かれているので、行かれた際にはそこも見ることをお勧めする。無料で拝観できる。御朱印を頂き、お寺の方とお話ししている中で、ご本尊の一つである千手観音菩薩の札があることも知る。それも、とお願いしてただだと勘違いしているわたしに「100円です」と慌てて言われて苦笑した。お金に疎い自分がいつまでも子どもじみているように思われて恥ずかしい。反対側にある売り場で、腕輪のようなお守りも購入した。
鞍馬寺はまだ終わらない。ここから更に奥の院へと向かう山道がある。ここは義経の修験道だったとも言われ、特に下りが険しい。下ると反対側の貴船神社に行く道に出る。川床の料亭が軒を連ねる場所だ。その山道は踏み固められ、石の階段も作られているので歩くには難儀しないが、素人にはその落差、段差が足にくるのである。初めて一人でここを降りた時には、地上の門を出る時には体が悲鳴を上げていた。去年知り合った古武術の体操で多少鍛えられたとは言え、実態は前回とさほど変わらないだろう。明日は秦氏の古流武體術だから、鍛えておかねばなるまいという信念が湧いていた。奥の院では特に何も感じられないのがわたしの常である。一通りお参りして、ひたすら貴船を目指して階段を降りた。
貴船神社は、清らかな水の氣が流れる場所だった。三連休で晴れていたこともあり、狭い道路は車と人がひしめき合い、時折、氣の短い運転手が怒鳴って緊張が走る。疲れた足を引きずりながら、満席の川床料理を何軒も断られ、手軽な軽食が食べられる川床のお店に落ち着いた。川床を一度体験してみたかった。貴船駅まではかなり距離があるが、この道路の混み具合では歩いた方が早いと思い、痛む足をなだめながら駅まで歩くことに決めた。その途中で、バスに抜かされた。多少混雑していても、貴船駅まではバスに乗ることをお勧めする。
市内に戻り、八坂神社の前に差し掛かった所で祇園祭なのだと氣付いた。せっかくなので歩いてみよう。人で溢れる大通りを相当歩いたが、祭りの熱氣に興奮して体力の限界は吹き飛んでいた。
この祭り中にしか売っていない魔除けのお守りなどを目にして、地域の人との話に花が咲く。暑さにむせ返る西日の中に、祭りを見物に来た多くの人達が去来する姿を見て、この一人一人が誰かにとっての大切な人なんだと思うと、世の中はそう悪い場所ではないと思えてくる。

【うさこの本棚】(本の宣伝です)

『シーラという子』トリイ・ヘイデン著、ハヤカワ文庫NF。
中学生の時に司書の先生が取り揃える本が面白くて読書が好きになりました。中学生の時に出会って大好きになった本は何冊もあるんですが、『シーラという子』はその中の一冊です。従兄の家が家庭崩壊を起こしたこともあり、当時は明確に言葉にはしていないものの、虐待とか養育不全に陥っている家庭の子どもに関心がありました。
シーラもそういう子どもで、結構大変な状態の子どもだったと思います。そのシーラに対して、特別支援学級の教諭でもあった著者が心を砕いて関わっていく実際にあったお話です。
著者のオムネク・オネクさんは金星から地球人のシーラと入れ替わった金星人なんですが、老齢が近づく頃の聴き取りで、もう一度地球人に生まれ変わりたいかと聞かれて、「大変だったのでもういいわ」と答えていました。そうだよね、と心の中で呟きました。この本では幼少期のシーラしか綴られていないので、その後どんな生活を送ったのかは知る術がないのですが、もしこういう世界に少し関心があるならば、読んでみるのもいいかもしれません。
わたしが読んだ頃はもっと怖い装丁の単行本だったのですが、今は文庫版になっていました。早川書房さんだったんですね。外国語のノンフィクションに強い出版社さんの印象があります。
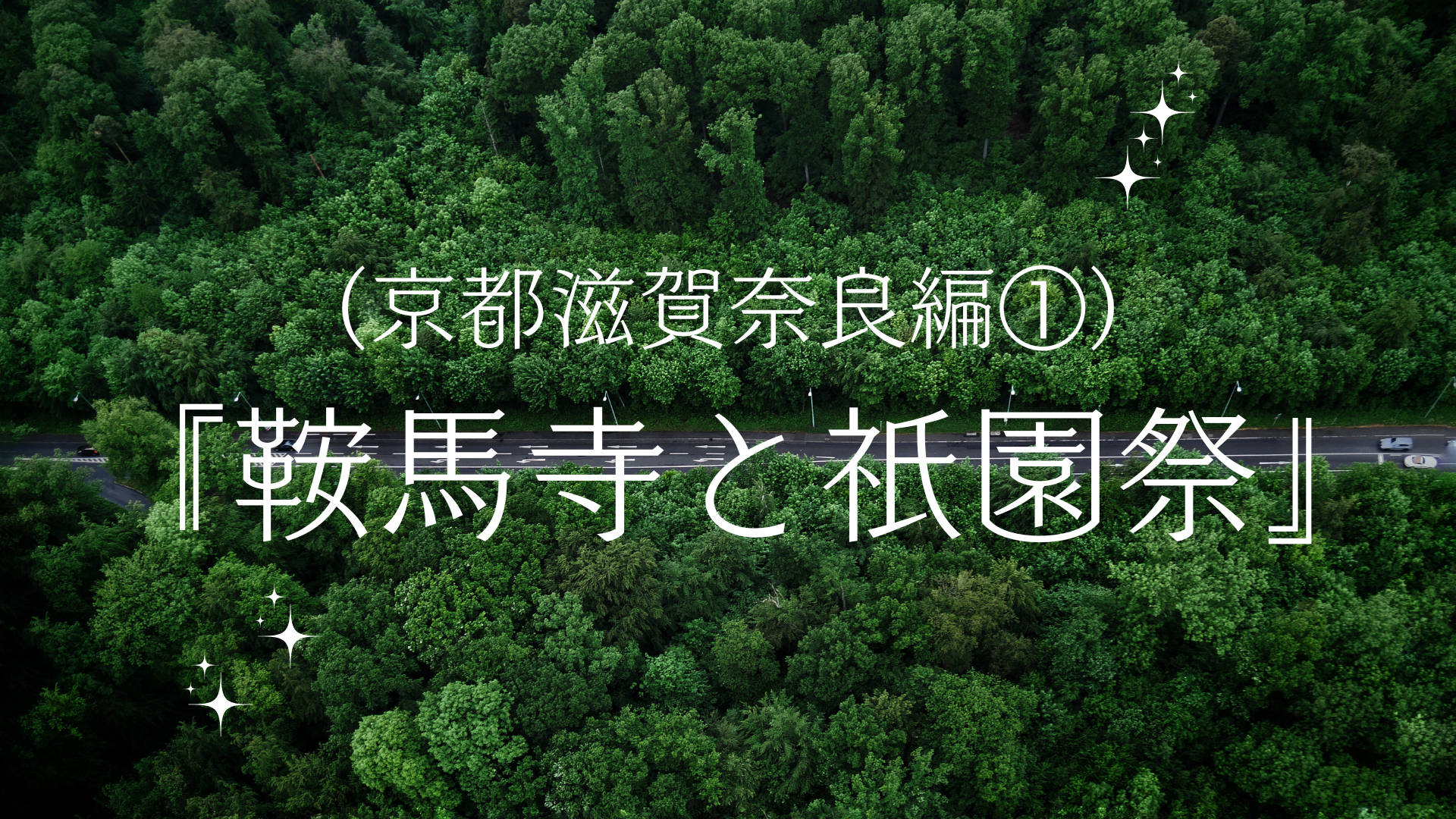
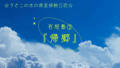
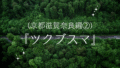
コメント