はじめに
ツクブスマ姉妹についてはこちらから。
丹生川上神社下社を勧められた経緯はこちらから。
前回の記事はこちら。
『神へのきざはし』
「丹生川上神社下社に言ったら、宮司さんとお話ししてみて。私の名前を出してもらっても構わないから。」
この神社を紹介してくれた女性は、そう言ってわたしに念押しした。それほどまでに強く勧める宮司さんってどんな人なんだろう。どんな話をするんだろう。そもそもどんな神社なんだろう。宮司さんと話す、その情報のみで、何がある神社なのか全く検討がつかないまま現地に向かう。
いよいよという氣持ちで鳥居をくぐると、境内にはやや小柄だが白い馬と黒い馬がいる。白馬が柵の近くにいて、近寄ると挨拶をしてくれたので、しばらく馬を眺めていた。そしてゆるゆると手水舎に向かう。手水舎には他に一組の初老のご夫婦がいらした。その時、私服姿の男性がご夫婦に話しかけてきた。そしてわたし達にも声がかかる。これからお参りですか。そんな感じだったと思う。はい、こちらの神社に来たことのあるお友達から勧められて、初めて来ました。そうですか。そんな会話をしながら、ご夫婦と一緒に本殿に向かう。「こちらへ」と言われて5人で拝殿の中に招かれる。靴を脱いでちょっとした階段を上がり、椅子に座ると男性がおもむろに話し始めた。
この神社のこと、神社の由来、「言上げせず」の精神について、そして拝殿から本殿へと続く長い階段のことと、奈良から京都市内そして福井県の沖合に浮かぶ御神島まで、少しずつ誤差を含みながら聖地を結ぶ一直線の線が引けること、その線とこの神社の階段の向きが一致していること。
遠くで雷鳴が轟く音がする。雨は降っていない。何だか神様のお知らせみたいだ。
この神社がそんなにすごい階段を擁する場所だったなんて。わたしには、この神社が聖なる直線の起点になっているように感じられた。
男性の話に圧倒される。その一方で、心の中で一つの疑問が浮かんでいる。
何だか作業着みたいな格好をしているけど、これほどの話をするんだから、このおじさんが宮司さんなんだよね。男性の話と自分の脳内に響く疑問の声が二重写しになる。
やや経ってから、「私が宮司です」と名乗りがあった。友人から聞いていた名前と同じだった。やはり。
そこからさらに、宮司さんの経歴やこの土地に宮司としていらした経過などを聞いた。宮司という職業や神社の仕事について改めて聞くことは初めてだったため、当事者の話をここまでざっくばらんに聞くことができる機会がありがたかった。
息子さんの話、第二次世界大戦のこと、自分が今まで触れてきた歴史観や知識、価値観と照らしながら、宮司さんの話に耳を傾けてその差異に驚いたり内心ぎょっとしたり、色々な意味で面白く興味深かった。わたし達が話を聞いているのを見て、参拝に来られた方々が自分達も話が聞けるのかと思い声をかけてきても、その宮司さんはお断りをしており、何らかの基準かたまたまそこにいたという条件か何かが整わないと話が聞けないようだった。そういう意味でついていた。
さらに驚愕なことに、今日はその階段の御簾の向こうに入って直に階段から本殿を見上げてお参りして帰ってくださいと告げられる。御神島の絵が描かれた棟木に垂れ下がる御簾は閉じられており、これからそれを開いて参拝のための準備をするという。
ええっ。いいの。
とても神聖な階段ではないのか。宮司さんがいいと言っているとは言え、恐れ多くて氣が引ける。座布団を御簾の中に差し入れ、簡単な準備が整えられていく。順番にどうぞ。最初はご夫婦から、そしてツクブスマ姉、次にわたしの順番が来た。
恐る恐る御簾の内側に入り、座布団に正座する。階段には壁がなく、両側に生える樹々の緑が光を透かして風に揺れている。心の中がその光と葉の色と動きで染まる。
そして本殿を見上げた途端、突然、とてつもない感謝の念に襲われた。
ここに座ることができているのはとてもありがたいことなのだ。
こんなにありがたいことはない。こんなに光栄なことはない。言葉にならない想いと共に涙が溢れてくる。震えながら叩頭し、しゃくり上げるように泣いていた。
見上げた本殿は遥か高みにあった。
席に戻ると、わたし達3人はみな泣いていた。
宮司さんと質疑応答をしていると、今度は大きなカマキリがわたし達が話を聞いている拝殿に入ってきた。あちこち歩き回り、話はカマキリ捕獲で一時中断した。神社で出会う虫もまた、神様の使いだと聞くことがある。お使いが沢山来る。これも神様の采配なのだろう。
帰る時、できるだけ感謝の意が伝わるように鳥居を一歩出て振返り、居住まいを正す。そして心を込めてお辞儀をした。
Facebookはこちらから。
インスタグラムはこちらから。

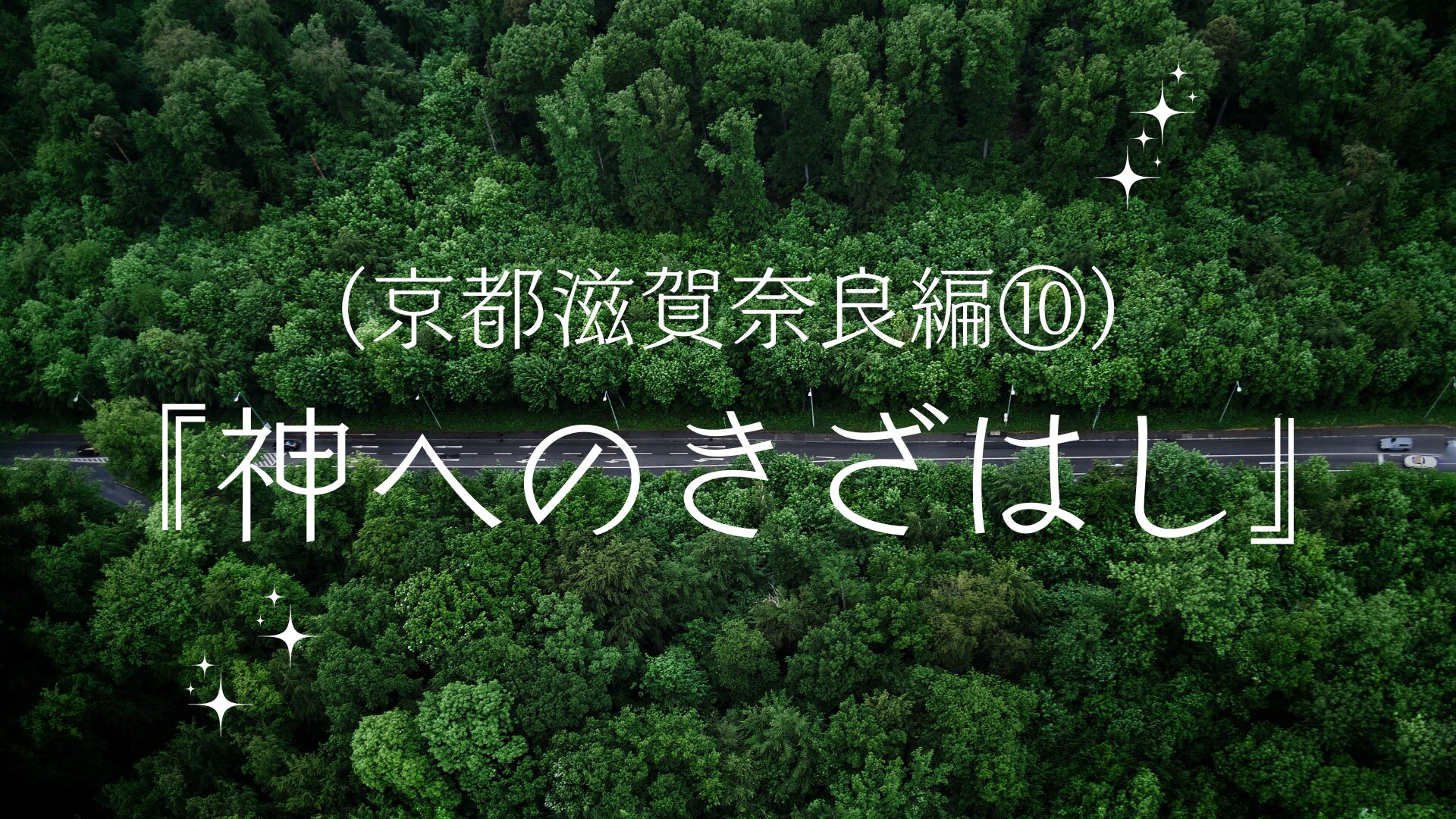
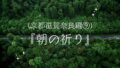

コメント