はじめに
料理教室で習った絶対に美味しくできる親子丼を作ったら、何だかしょっぱくて変だなあって思ったんです。よくよく考えたら、鶏肉を入れ忘れていたうさこです。
さて、2025年の9月に、書店の店員さんと興味深いおしゃべりをしました。思わず備忘録として、ここに書きます。
本屋さんって、社会全体の知的水準を保つ機能を果たしていると思うんですが、その書店の経営が今、想像していた以上に苦しい状況に置かれているんですね。それを肌身で感じました。そして、その店員さんとのお喋りがさらに興味深かったので、ぜひ読んでくださいね。
『書店の事情』
前月号の書道の専門雑誌を買い逃してしまい、バックナンバーの注文をしようとして、本屋の窓口で手続きを取っていた時のことです。書店から取扱っている問屋さんを見つけるのに少し手間がかかりました。
なぜかと言うと、今は出版での売上が減少しているため、どこも経費節減のために出版社や問屋さんが本の在庫を持たない方向で動いているからであること。そのため紙の本や雑誌、漫画も含めて、過去に出版した本が手に入りにくくなっているのが現状だと言うのです。漫画でさえ、ものすごく売れているにも関わらず、完結したら重版をかけないこととかがざらにあるらしい(そしてやっぱり、丸谷才一さんの『新々百人一首』新潮文庫版は絶版になっていた。悲しい)。
欲しかった雑誌は、取引のある問屋さんでは在庫なし、別な問屋さんで在庫を確保してもらえました。「送料等で書店の儲けは出ませんね」と言われ、少し恐縮しました。「本が好きだから、続けているんです」と。本はそれほどまでに利益が出なくなっているんだと、現実を垣間見て言葉が出ませんでした。
さらに、じゃあ電子書籍はどうなのかという話をしたところ、その店員さんは本と読書が好きらしくて、スマートフォンなどの小さい画面で文章を読んでいると、視野が狭くなって頭に入りにくくなること、視野が狭いと人との会話や集団競技などの運動面でも支障を来す恐れがあるんですよなんていう話を突然してこられたんですね。それはわたしの周囲からも聞く話だったんです。スマホだと画面が小さい分、短い文章しか読めなくなるんですってね。わたしはiPadminiまでしか持っていないので、電子書籍は書籍と同じ大きさで読めるからよく分かっていませんでした。
また、子どもの頃に動画などを四六時中手放さずに休みなく見てしまうことで、前頭前野(理性や我慢する力を司る)が育ちにくくなり、長期的な目標に向けて目の前の快楽を我慢して勉強することとか努力することができにくくなるという調査結果があるらしい。
加えて、スマホの常時使用児群と無使用児群を5年間比較追跡調査した研究では、前頭前野(だったと思う)の発達に30%の差が出たそうで、子どもの脳の発達においてかなりな差が生じるらしいことなど、詳しく話をしてくれました。スティーブ・ジョブスやビル・ゲイツが、自分の子どもには中学生ぐらいまで端末を持たせなかったのは有名な話です。
お子さんを持つ方は、とても氣になる話題じゃありませんか。
スマホやSNSは依存性が高くなるように設計されているって言いますし、事実その手の本を読むとそのように研究されてきた経過が書かれています。わたしもやりたくないことから逃避したい時は結構端末を触ってしまいますもん。
反対に、本を読む時は印刷された白黒の文字から五感を総動員して自分の中に世界を想像する必要があること、また視野もスマホの画面よりは広いことで、自分の能力を鍛えることができるだろうということでした。
店員さんは速読ができるらしく、本の内容にもよるけど、一冊30分位で読めてしまうらしいです。わたしも、退職後に速読を習得しました。通常の本なら一冊一時間前後かな。速読ができると脳の処理速度が上がって世界の見え方が変わるよね、本によって開ける世界があるよねという話で書店員さんと意気投合しました。結構な知的興奮がありました。
あらゆる媒体が発達して出版文化や読書文化が衰退傾向にある昨今のご時世において、これほど本に熱い人に出会えて熱く語り合えたのがすごく嬉しかった。面白い人を引き当てたなあって、そっちも楽しかった。出会いは必然。いつか、読書と速読と子どもの能力の育て方について、わたしの持論を話す会などをやりたい。この店員さんも協力してくれないかな。
ていうか、わたしの読書に関する持論って興味ありますか(笑)。
うさこの本棚(本の宣伝を含みます)
『監視資本主義』ショシャナ・ズボフ著、野中香方子訳、東洋経済新報社
LINEって、何で無料で使えるのか知っていますか。InstagramやFacebookが無料なのもどうしてなんでしょう。考えたことってありますか。
わたしもそんなに大して考えることもなく、氣楽に使っていました。
そんなところに、なぜか政治情勢に詳しいお友達のおじさま医師からお薦めされた本がこちら、『監視資本主義 人類の未来を賭けた戦い』です。副題が物々しいですねえ。
読んで驚愕でした。
Googleマップを始めとするGoogle社のサービスも、ルンバも、ポケモンGOも、行動情報を取得し収益化するための道具だったなんて。
帯に「オバマ元大統領が選ぶ2019年ベストブック選出!」ってあるけどさ、ちょっと白々しいんじゃないかなあ。オバマさんはこの仕組みを利用する側にいたでしょうに。
これは、うかうかしていられない氣がする。そう思って知り合い達と話をし、ついでにこの本を読んだんだよって伝えたところ、「まあた、難しい本を読んでいるわねえ」とおばちゃんから言われたのでした。
お値段は高いし、内容はちょっと難しいかもしれないけど、世界を見る目がぐんと深くなります。読む価値ありですよ。
『スマホ脳』アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳、新潮新書
そして、携帯端末の依存度の高さに分かりやすく警鐘を鳴らしたのが、こちらのアンデシュ・ハンセン著『スマホ脳』です。
携帯端末がどれほど依存性を高める作りになっているのか、わたし達の脳と体にどのように影響を及ぼすのか、集中力をどれだけ削ぐのか、子どもの発達への影響は、などなど、読んでから自分のスマホ依存度にはっとした一冊でした(今もはっとしている笑)。
全世界でも日本でも、かなり売れた本みたいです。新書なのと、内容も文章も簡単な表現が多かったので、スマートフォンの依存性について概観を理解するのに最適です。
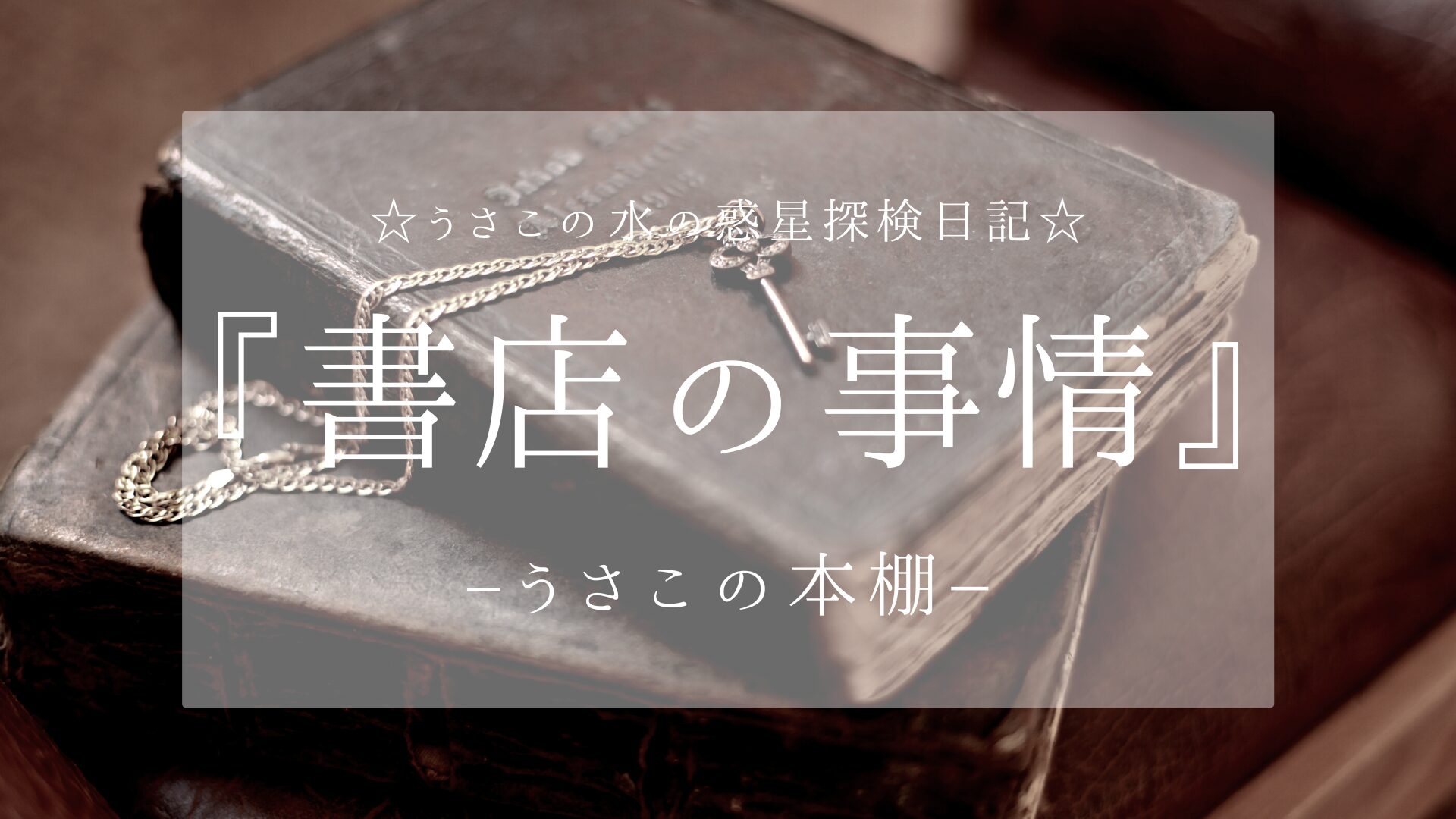

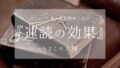
コメント