體術の二回目に合わせて、一月後に再び京都を訪れた。
今回も東京から夜行バスで朝7時前の京都駅に着く。そこからまた鞍馬寺を目指す。京都と言ったら鞍馬寺。あの山の上の拝殿に惹かれてしまう。
毎度、京都駅から一時間程の外れにあるこの山によく登るものだと自分でも感心する。まして、不眠氣味な上に眠りずらい夜行バスでの長旅の後である。加えて夏の盛りの暑さも手伝い、体はへろへろで、ケーブルカーにも乗らず徒歩で拝殿まで登拝する。そして迷うが、できたら鍛錬の一環として、また山越えをして山の反対側の貴船神社に行きたい。そんな物好きなわたしは変態だろうか。
鞍馬寺に向かう途中、叡山電鉄に乗り換える出町柳の駅で下鴨神社の最寄駅であることを知る。源氏物語でも正妻葵上と年上の愛人である六条の御息所の勢力争いが描かれた葵祭が有名である。よく調べていないが、かなり由緒ある格式高い神社だったのではないだろうか。10年以上前に一度、上鴨と下鴨どちらも行った氣がするが、土地勘も神社の形も全く覚えておらず、帰りにお参りしてみようと思う。
再び鞍馬寺駅に着き、徒歩で入口の石段を登る。そこから大きな山門を通り、愛山費500を支払う。その時に頂く季節毎のしおりに書かれた和歌が、ささやかにも楽しみである。ゆっくりと樹々の緑を感じながら、深呼吸をして山の空氣を味わう。この神聖な鞍馬の山の氣を頂くために。そうしてまた、息を切らせて山頂の拝殿に到着する。夏になって少し暑くなってきたので、午前中と家でも汗だくになる。ふらふらの体を休ませて、長椅子に座って水を飲んでいると、息を切らせた登拝者が次々と登ってくる。みなさん、お疲れですね。しばらく山の空氣に触れて、猫背で落ちそうな程に頭をもたげた虎の狛犬と灯籠に挨拶をする。今日はそこまでお喋りではない。けれども、変わらずに本殿を守っている。金剛床と呼ばれているらしい魔法陣のような円の中心に立つが、毎度のように何も起こらない。そうやってのんびりと本殿に入る。
お参りの後に、おみくじを引く。そして御朱印を頂いて、前から氣になっていた天狗の扇と腕輪のような御守りを買う。普通、御守りは一年毎に新しい物に変えるように言われるが、この天狗の扇は逆で、ずっと持ち続ける物だと言う。できたら目線より上の清らかな場所に飾るといいそうだ。お経が書かれた太い蝋燭も氣になるが、値段と重さを考えてぐっと堪えた。地下の拝殿に行き、また奥の院から貴船神社への山越えを目指す。わたしは奥の院でも特に強い氣を感じられない。この一ヶ月、體術の鍛錬を続けたが、相変わらず山道は体にこたえた。無事下山し、貴船神社に簡単にお参りしてから、今回は貴船駅までバスに乗った。先月の帰路を思うと、快適だった。
そして出町柳駅で下車して、下鴨神社へ向かう。正式名称は賀茂御祖神社と言うらしい。一度来ているはずなのに、こんなに山道が長くて広かったのか、初めて来た場所のように全く記憶にない景色ばかりで浦島太郎状態だった。確か別途拝観料を払って、国宝の本殿二棟の公開にも参加した。賀茂別雷大神とか、初めて聞く神様の名前やその家族関係なんかの説明を受けたが、そもそも神様の名前には疎く、知らない神様情報は多少抵抗してくれた物の脳内を素通りしていった。神話が好きで沢山の神々の名前を覚えている人がいるが、そう言う人をすごいと思う。
元来た参道を戻ると、途中で茶室等を公開している建物があり、そこにも寄ってみる。平安時代以前の記録は定かではないらしいが、ここは門前町のように神社関係者が屋敷を連ねた所で、位の高い方々が住まい、神社に奉仕した屋敷の一つだと言う。壁、柱、茶室から道具類、建物のしつらえまで、どんな人々が住み、下鴨神社に仕えたのか、想像を掻き立てられ千年以上昔の時代に思いを馳せる。
京都には時間が堆積している。この限られた土地に、古くからの歴史と時代が地層のように空高くまで積み重なっている光景が思い浮かぶ。

わたしは知らなかったけど、素敵なお茶処などもあるみたいなので、あらかじめ見所を調べて行った方が楽しそうです。





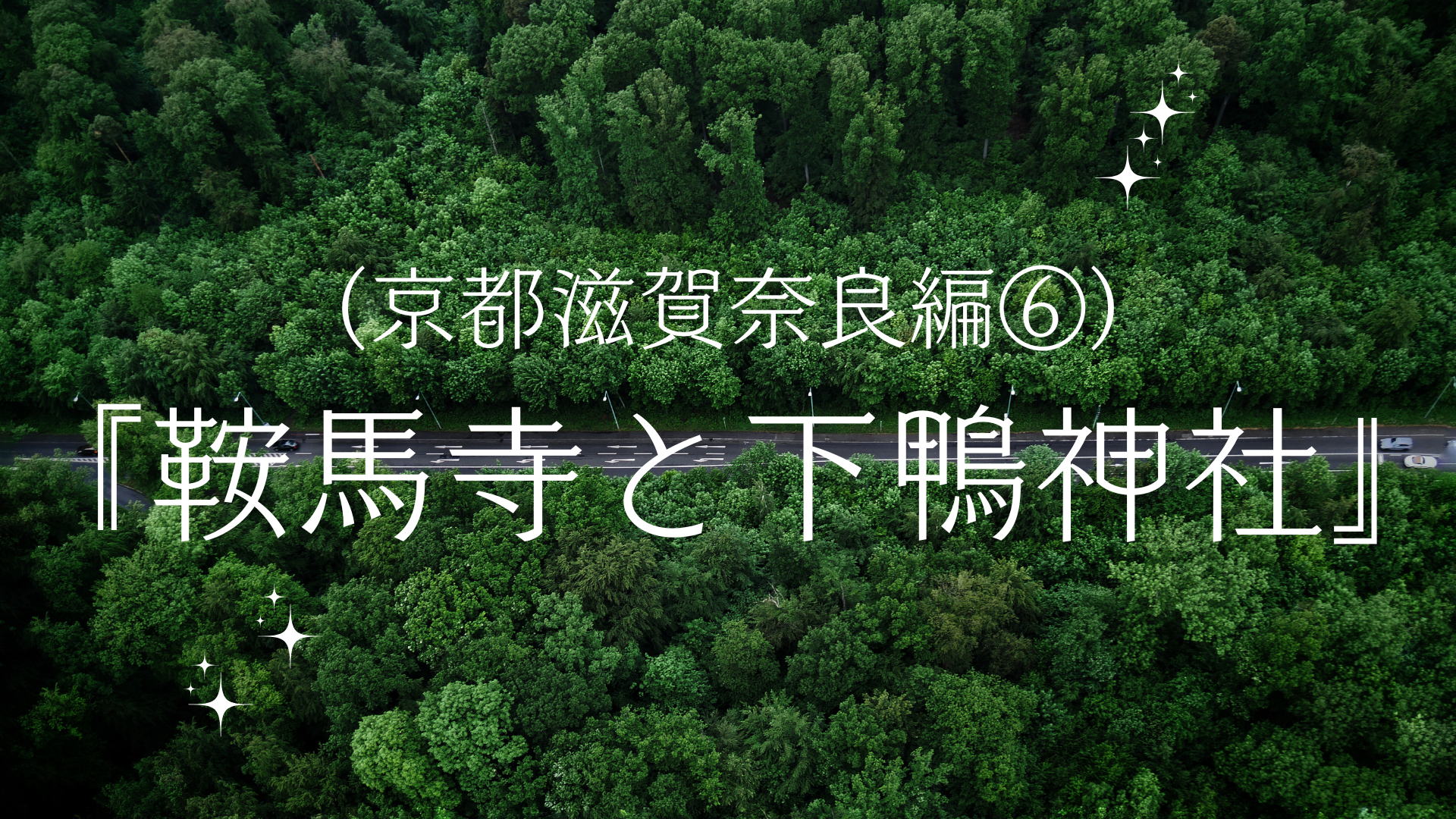
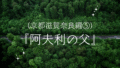
コメント