はじめに
前回の記事はこちら。
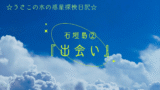
『年老いた少年』
本の中の写真の人と比べると、髪の毛も髭も少なくなっているように見えた。そう言うと、「それは10年ぐらい前の写真だからね」と言われ、なるほどそう思ってよくよく見るとその老人のもう少し若い姿だった。
老人は、出身地にある最下位の高校を出て海の仕事に就き、父親の急逝を機に仕事を辞めて独立企業した。勉強はできなくても実学のある人で、独立したての若い頃はお金もなく、目的も当てもなく麻雀をして時間を潰したり、東南アジアの島々で仕事のない冬場を凌ぐような日々だったらしい。
けれど、その本で紹介されている物に出会い、腕を磨いているうちに隣に並ぶ者のいない力を付け、その世界の英雄になっていた。元来、穏やかで愛情深い性格に加えて、学はなくても話が上手くある世界に精通していたから、人に囲まれ慕われていた。学ぶことは多かった。
趣味は海で遊ぶことだった。また、色々な所へ旅をしていた。
わたしが行ったことのない小笠原諸島やトカラ列島、沖縄の島々、そして東南アジアの名も知らない島々のこと。女将さんも他の客も、東南アジアにはよく足を運ぶらしい。俄然、これまで全く視野になかった島への旅行が氣になり始めた。わたしの知らない世界がまだまだこんなに沢山あるんだ。
好きなことをするために仕事を頑張り、収入の道を作って、誰にも邪魔されずにやりたいことをやって楽しむ。老人は、そんな生き方を体現していた。でも、有名になるとその分制約が増えるから、絶対に世には出ないのだと。有名になることよりも、自分の好きなことをして生きる自由を何よりも大切にする。自分の想いを生きている。その考え方、生き方にとても刺激を受けた。本当にすごい人は、表に出ない。それは本当なんだなと目の前の老人の存在が語っていた。
わたしはここに来る直前に、カフェのご主人こと「石垣の監督」から言われたことがずっと心に引っかかっていた。『常識がない、普通の人達とのお付合いができない、社会との釣合いが図れていない危ない子になりかけている』ことだ。社会人経験を経て常識の土台を作った上で、自分が好きなことをして生きたいと思って決めた退職だった。普通の人達とのお付合いが窮屈で仕事を辞めたのに、辞めた先でまた我慢をしなきゃいけないのか。それが大人として世の中を生きていくことなのか、煩悶していた。そんなことを言われたんですよとこぼしたら、そんなことはないでしょと口々に言われた。うさちゃんは辞めてよかったでしょう、そう思うよ。老人も含めてそこに集まっていた人々はみな、経済状況はそれぞれであっても、自分の世界を作って好きなように人生を生きている人ばかりだった。その顔を見て、内心笑ってしまった。場所が変われば、人の意見は正反対に変わるのだなと。どちらも正しく、どちらも間違っていない。どこに身を置き、どの世界で生きたいと思うのかの違いだけなんだと思った。わたしの心は少しずつ軽くなっていった。
ある日、来客があって老人の海遊びに繰り出すついでに、わたしもそこに混ぜてもらえることになった。老人は、「あなたはそのお客さんのついでのついでの、ついでだからね」と勿体ぶって恩を着せてくるので、はいはい、そうですねと軽くあしらって遊んでいた。当日、その客から「うさこさんは、どうやってここに」と聞かれて、何も知らずにたまたま選んだ日程が老人の滞在と丸々重なっていた旨を説明すると、「そこであの方を引き当てられるのがすごいよ」と言われた。その客も、ある界隈では有名な人らしい。はたと我に返る。老人の実績を考えるとすごい人だとは思うけれど、確かに偶然とは言っても、そういう人と出会ったことはすごいことなのかもしれない。しかも、わたしはなぜか絶対にこの日程でこの宿に行くと決めていて、銀さんが心配して声を掛けてくれた日程を断っていたから尚更である。20代の頃にも似たようなことがあった。自分ではそんなつもりはないのに、すごく大きな人物を引き当ててしまったことが。あの時に似ている。人生は不思議なものだ。
初めて出る石垣島の海はとても青くて透き通っていて、それよりも初めての体験に心が躍った。海に潜ってきらきらと輝く大小様々な魚の群れをいくつも見て、海底に落ちていく珊瑚の岩棚やそこに寄せ集まる見たことのない形をした珊瑚を沢山みた。どうやったら海中を疲れず早くバタ足で移動できるのかを考えたり、初めての海遊びで新鮮な体験を沢山した。とても楽しかった。海水温が寒く感じて船の上で船内の設備を物色していると、老人から「うさこさんは帰ったら何をするんですか」と聞かれた。言いたかったが、ぐっと喉元でつかえてしまって言葉が出なかった。
夜はみんなで夕食の餃子を皮から手作りして食べた。わたしは小麦粉から延ばされた餃子の皮を包む人に運ぶ係をする。包むのは老人とフラダンサーの男性の二人である。老人は包むのが嫌に速いので、男性で餃子を包めるのは珍しいと思って褒めた。「昔、中華屋をやっていたんだよ」と今の仕事とは全く関係のない業種の話をする。それに包むのは速くても、この不揃いで形もひだも雑な包み方は、絶対に嘘だ。ここ数日のゆんたくで老人の仕事振りや物事の判断基準を聞いた限りは、商売でこんなに雑で程度の低いことをする人ではない。この老人に限ってあり得ない。「絶対に嘘ですよね」「いや、本当だよ」と沖縄地方の抑揚でさらにとぼけるので、「この餃子でですか」と言外に畳み掛けるわたしを、フラ男爵が「そこまで言わなくても…」と取りなそうとする。この程度でおどおどする必要なんてないですよ、ふん。そう胸の内側で息巻いていると、老人が「だから潰れたんだよ」と氣の抜けた調子で言い放ったので、床に崩れ落ちて笑った。
沖縄や八重山諸島は紫外線が強いので、肌はすぐに焼けて黒くなる。その時、この宿に集まっていた人達は総じてそんな人達ばかりで、純粋な日本人なのに役場でフィリピン人と間違われて片言の日本語で話しかけられたとか、老人が昔、タイに滞在中に原付にまたがって日本の新聞を読んでいたら、若い日本人環境客の女性に「すごおい、日本語が読めるんですかあ」と聞かれて、無言で頷き返した話とか、その場面を再現する老人の仕草が絶妙で、そんな話をしてみんなで笑い転げた。女将さんの手作りの夕ご飯を囲みながら、時には人生の深い話、時にはそんな笑い話、それぞれの色んな話をして夜が過ぎた。でも海の上で老人から投げかけられた問いに、わたしはまだ答えられずにいた。
石垣島での滞在中に、わたしが本当にやりたいことをこの英雄たる老人には言っておこうと思った。他の人にまで言う勇氣はないけれど、老人だったら聞いてくれそうだった。ある夜、就寝でそれぞれの部屋に戻る時に、玄関の外に出た老人を追いかけて、わたし実は~になりたいんですと心の奥にある想いを絞り出した。それを聞いた老人は、少年のような顔をして瞳をきらきらさせた。これは、老人の心の輝きだ。きっとこの人は、こうやって夢に心を躍らせながらこれまでの人生を生きてきたんだろう。そうだったんだあ。うさこさんも胸にそう言う想いを抱いている人だったんだね。島の生き物の氣配が漂う外は暗く、玄関の灯りだけがぼんやりとわたし達を照らしている。その暗がりの下に浮かんだ老人の口調は穏やかで、数々の冒険を踏んだ少年と老人が入り混じったような表情が脳裏に強く焼付いた。
退職する時に、「感動して生きていたい」と思った。「もっと広くて豊かな世界を見てみたい」と。夢がまた叶った。
中に戻ると涙が溢れた。
女将さんと残った他の客に氣付かれないように、わたしは台所に入り、さっきまでみんなが使っていたコップを泣きながら洗った。
【うさこの本棚】(本の宣伝です)

この老人は無名であることを好まれる方なので、老人繋がりでこちらの本を紹介します。
大古典のアーネスト・ヘミングウェイ作、『老人と海』(小川高義訳、光文社古典新訳文庫)です。
これは各出版社で開催される「夏の100選」的な中から選んだ一冊だと思うんだけれど、その痕跡がどこにもないので、何かで氣になって買ったんだろうか。
なぜこの新訳を選んだのかは、帯にあるように「しかし作品本来の姿は、老人の内面のドラマを淡々と描いた、極めて思索的なものだ。原文に忠実な翻訳で浮かび上がる老人のこれまでとは異なる魅力に読者は魅了されるだろう」に惹かれたからだと思う。読後感はまさにその通りの感覚が残っていた。呆氣に取られた、呆然とした。そんな体感がしたのを覚えている。
八重山の島々を船で渡り、少しでも海の上の景色を味わった今は、さらにこの老人がいた海の上が身に迫って感じられる。物語が最高潮に達した時にも手に汗を握っていて、老人が達成したのを知って大きなため息をついたのに、本はまだ半ばで、「頁数が残り半分もある…」とその後の展開に不安になって心の中で呟いた記憶がこびりついている。その後半が信じられない流れを描く。
ヘミングウェイはこの作品をきっかけにノーベル文学賞を受賞しているんですね。知らなかったかも。『武器よさらば』『誰がために鐘は鳴る』も読んでみようかなあ。
もし何か読む本がなくて退屈しているならば、古典文学がおすすめです。いつかうさこの本棚でも紹介したいと思うけれど、『赤毛のアン』もそうでした。こんなに面白かったなんて、わたしはどうしてもっと早くこの本に出会っていなかったんだろうと後悔したのを思い出します。長い年月の風雪に耐えて残った名作は、読者の好奇心に耐えうる名文と名場面を備えてあなたを待っています。

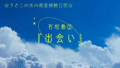

コメント