はじめに
前回の記事はこちらから。
『最南端』(波照間島で③)
波照間島最終日の今日は、有人島としての日本最南端を目指す。宿のご主人にそう伝えると、靴は頑丈な物を履いていくように言われた。かなりな岩場なのだそうだ。電動機付自転車で島内を一周するため、海には入らないがラッシュガードで身を包む。沖縄本島以南の島に滞在したことがある方ならお分かりになると思うが、この南の島々に照り付ける太陽の日差しは本当に強い。露出している肌はすぐに焼けて黒くなるため、手はラッシュガードの形に指だけ黒くなり、足首より下は線で区切ったように焼けてビーチサンダルの鼻緒の形だけが足の甲に白く残る。日焼け止めと同時に布地で素肌を守るのは必須である。特にわたしは肌が刺激に弱く、使用している自然派の日焼け止めは日焼け防止効果が薄く汗にも弱いので尚更だ。こうして夕方の船で石垣島に帰るまでの時間を島内最南端散策に充てた。
島に慣れてきたこともあり、今日は一度ニシ浜の方まで自転車で下り、浜の近くの食堂で昼食を食べることにする。前回の記事(こちら)で島の食事について書いたが、特に人氣店の予約が取りづらいこと、集落から離れた店は夜は送迎も可能だが人数が二人以上などと条件があり、一人旅には融通が効きにくい等という事情があるものの、選ばなければ食事に困ることはないと思う。昼食に選んだお店は畳の上がりになっていて、海水浴後の水着やラッシュガードのままでは入店不可である。服装から店員さんに警戒されたが、入水していない旨を伝えて上がらせてもらう。名前を忘れたが本州で言う豚丼のような物とマンゴージュースを頼んだ。確か黒糖で甘味付けをしていたような氣がする。そこが売りだった。
さて、腹ごしらえも済んだところで、いよいよ有人島最南端の碑を目指す。集落から離れて島の南側に向かうと、自然とサトウキビ畑の中の道を通ることになる。昨夜、あんかけ焼きそばを頂いた居酒屋の店員さんによると、八重山の島々にはそれぞれの島毎に産業があるそうで、そこからすると波照間島はサトウキビということになるだろう。航空写真を見るとよく分かるが、サトウキビ畑が綺麗に区画され、戦後のある時期に産業化を目指して大規模な区画整備がなされたことが推察される。島で食べる野菜等はどこで作るのかと尋ねたら、誰かが石垣島から運んでくるのだと言っていたような氣がする。食糧は島で自給しないのかな。現代化の匂いがする。
そんなことを考えながら少し走ると、立ち並ぶ電柱とそこに走る電線と、背丈の高いサトウキビの風景に出くわした。日中の暑い時間帯だからか、広大なサトウキビ畑に人の姿はない。カンカンと照り付ける太陽の下で、空に向かって伸びるサトウキビだけが延々と連なる音のしない、人の氣配もしない不思議な光景が続く。知らない世界に迷い込んだようだ。誰がこれらの畑を管理しているんだろう。隣の畑同士で農家さん達がお喋りをしたりしないんだろうか。そう思う位に閑散としている。農家の方を見かけたのは一人だけだった。その風景の中で一人電動自転車を漕ぐ。何にもないが、旅を終えて覚えているのはこういう景色だったりする。そしてアダンの街路樹が続く道。ここで数少ない二十代の恋人達に遭遇し、内心少し恥ずかしくなる。わたしは一人で何をしているんだろうという氣持ちになりつつ、一人だけど旅を楽しんでいます、平氣なんですよという風を装いながら自転車を漕ぐ。一人旅を好むくせに、幾つになっても恥じらいが消えないのもおかしな話である。アダンにはパイナップルを大きくしたような立派な橙色の実が付いていて、これが食べられたら何ていいんだろうと思うが、この実は食べられないと言われていた。この記事を書くに当たり調べたところ、甘くて美味しいが繊維質が多く食べるには不向きなようだ。ヤドカリやヤシガニの餌となる。島では見かけなかったが、アダンの実を穂先にした「アダン筆」という物もあるそうですよ。
しばらく行くと島の南側に出たようで、日本最南端の公開天文台になる星空観測塔があった。集落から少し離れているので、滞在中に来ることは半ば諦めていたが、思いがけず来ることができて嬉しくなる。最南端の碑まではもうすぐだ。
最南端の碑がある場所は、白い砂浜が広がるニシ浜とは対照的な断崖絶壁で、足元は何の成分でできた岩なのか、黒くて雨風や波飛沫で削られるのか小さな突起が突き出てごつごつしている。風が強く、断崖から覗き込むと、崖の下には太平洋の外洋から打ち寄せる波が轟音と共に白く大きな飛沫を上げる。足元を見ながら落下しないように恐る恐るにじり寄る。濃く透明な青い海中にネコザメのような影が一匹、悠々と泳いでいた。地球には本当に多様な環境があり、様々な生き物が棲んでいるのだなあと感嘆する。南の眼前には、青い海が果てしなく広がる。空と海と風と波と崖、それ以外には何もない。これが波照間行きを決めた時に行こうと定めた最南端の風景だ。日本の最南端を制覇した。いつの間にか、最果てを攻略する人に変わっている自分に笑ってしまう。最果てを意識するようになったのは、菌ちゃんふぁーむでの出会いからだ。こういう出会いが自分を変えてゆく。だから旅は面白い。一応、最南端の碑で記念撮影をした。
そこから宿への帰り道の途中に、面白い看板を見つけた。「低潮保全区域」とある。詳しくは写真を参照の程だが、日本の領海や排他的経済水域を決定するために干潮時の海岸線の保全が必要となり、そのために海底の掘削や切土(こんな単語は初めて聞く)、土砂の採取、施設又は工作物の親切又は改築等、この区域における「海底の形質に影響を及ぼすおそれがある行為」に許可が必要となる場所を言うようだ。小学校だか中学校の社会科で習ったあれである。管轄は内閣府。すごく政治的な場所なんですね。面白い。わたしの後にも男性が一人看板を読んでいて、見ちゃいますよねと内心話しかけた。低潮保全など、ここじゃないと知ることのない言葉だ。
そろそろ宿に戻ろう。とにかく暑い。空氣もむっとすれば、日差しも暑い。近くの木陰でカラスと休む。カラス、だったと思う。暑さが手伝ったからか、島内一周はそれなりの距離があった。
港に向かう送迎の車中で、宿のご主人が港近くの海を指しながら「この辺でも昔は貝や魚が採れたんだけどねえ」と漏らすので、その理由を聞いた。すると一言、サトウキビ栽培を始めたからでしょうとのこと。わたしが石垣空港からぶうぶう文句を言われて乗せてもらったタクシーのおじさんが、通りがかったサトウキビ畑の農家さんと友達とのことで、サトウキビは肥料がないと育たないと話していたのを思い出す。化学肥料のことだろうと思う。それならば、恐らく農薬も使うだろう。化学肥料はその何分の一かは土中から地下に流れると聞く。雨で海にも流れるだろう。これは推測だが、そういった産業的な要因も海に影響しているのではないか。海産資源を守るために山に植林をしている事例もある。最近、食糧自給のこと、自然環境の循環について考えることが多い。目が醒めるような青い海が広がる最南端の島で、そんなことも考えさせられつつ、石垣島行きの船に乗った。







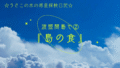
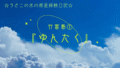
コメント